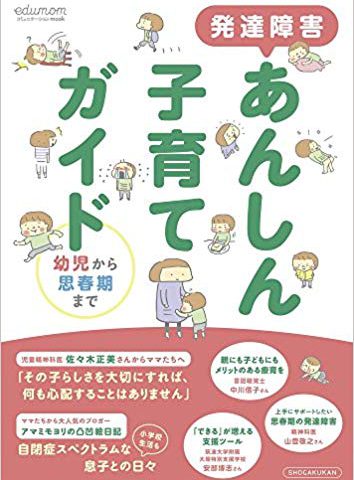自動下書き
トビラコへ、ようこそ
~店先で、ちょこっとおしゃべり~
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。
【お知らせ】
小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に
発達障害の子の学びは道具でサポートできる!読み書き困難をラクにするBest5をプロが厳選をアップ!
『ソトコト』7月号の特集「ウエルビーイング入門」でtobiracoが取り上げられました。
『PriPriパレット』(世界文化社)にトビラコ店主の「ちょっとためしてみませんか!」連載中

——————————–

通常学級以外の就学の情報というのは、なぜかあまりオープンになっていません。
通常学級の「入学準備」の話はいくらでもあります。でも通常学級以外に進むかもしれない子や親のための情報は、すごく不足しているんですよね。
『就学支援』というようなタイトルの本はいくつか出ています。この類の本は、1冊あるといいかもしれません。教育委員会に相談に行って就学先が決まるまでのおおよその流れは掴めます。でも、じつはこうした本だけでは、情報は不十分だと思います。
就学先の事情は、地域によってかなり違います。地元の情報を入手しないことには、判断がつかないこともあります。
例えば、今、特別支援学級は、その丁寧な指導ぶりが人気で定員に達してしまっている学校がいくつもあります。そうなると、通常学級でなんとかやっていけそうな子は特別支援学級に入ることはできなくなってしまいます。となると、通常学級での配慮はどの程度してくれるのかということを知りたくなりますよね。
通常級でギリギリついていけるかいけないかという状態で勉強するのは、子どもにとってはつらいことです。通常学級で難しくて、特別支援学級にも入れず、結局、特別支援学校に通うようになったら、子どもがイキイキしたという話も聞きます。だとしたら、最初から特別支援学校でもよかったのかもしれません。
ほんの一例ですが、このように地域によって事情が全く異なります。なので、早めに自治体に問い合わせて相談を受けるなりすることをおすすめします。
自治体のホームページで「就学支援」と検索すれば出てきます。教育委員会に「就学のこととで相談したい」と問い合わせてもいいかもしれません。
さらにいいのは、地元に学校の事情に詳しい人から話を聞くことです。地元で昔から活動している「親の会」なら、地域の学校の生き字引きみたいな人が必ずいます。こういう人から得られるのが最も価値のある生きた情報です。
就学支援に力を入れている幼稚園は園長先生もまた学校の生き字引きの場合があります。卒園生が入学した学校に頻繁に足を運んでいるからです。学校の先生とも顔見知りです。今年の加配の先生の情報、特別支援学級、通常指導教室の情報などよく知っています。ずばり、園長先生や担任に聞いてみるのもいいかもしれません。
いずれにしても、情報格差が生まれやすいのが特別支援教育の現状です。
トビラコ店主
********************************
ウェブサイト以外でも発信しています。
Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)
LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。
********************************
トビラコが編集した本
『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)
『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)