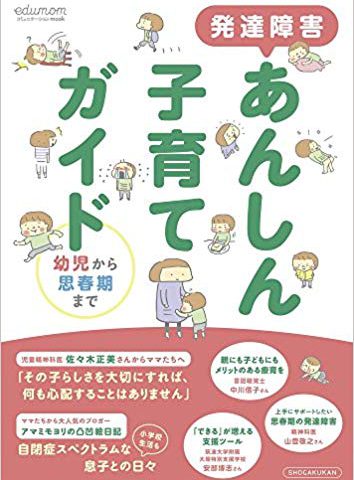トビラコへようこそ!
〜店先で、ちょこっとおしゃべり〜
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

・一見おとなしく参加しているように見えて内面では苦痛を感じながらじっと耐えていることがある。
・口頭のコミュニケーションだけでは情報をうまく取り込めないため、先生の指示を聞き漏らして伝達事項を親に伝えられない。
・提出物を把握できずに忘れ物が多くなるなどの問題が生じやすくなる。
自閉症スペクトラム障害の乳幼児期から児童期までの特徴とは〜学校生活を送る中でさまざまな”やりにくさ”を感じる〜本田秀夫
で挙げられていた学校生活で感じる自閉症スペクトラム障害の子の困り感です。
(これは、聞き書きかな。本田先生は「自閉スペクトラム症」という言い方だと思うのですが)。
自閉症スペクトラム障害の子にとって、学校生活は困難の連続ということを改めて認識させられる記事でした。

では、どのようにしたら良いのか。記事にはなかったので、かつて本田秀夫先生を取材したものとして、僭越ながら付け加えておきます。
●幼児期からお手伝いで役割を与え、評価される場面を作る。→自己肯定感が下がりがちなので。
●生活リズムを一定にして時間感覚を養う。
●学校以外に、いろいろな居場所を作っておき、時に逃げ場所にする。→学校だけを居場所にしない。
●苦手を克服させようとしない。→漢字、四則計算の反復練習は地獄。
●無理やり挨拶させない→意味不明ととる。声かけられたら返事するだけで十分。
放課後等デイサービスが少ない人数で療育を行うのは当然のことなんですね。人数が多かったら学校の教室と変わらないということになりますものね。
このところ、なぜか本田秀夫先生の記事が目に飛び込んでくるのでご紹介する次第です。
トビラコ店主
********************************
小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に連載していました。
********************************
ウェブサイト以外でも発信しています。
Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)
LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。
********************************
トビラコが編集した本
『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)
『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)