トビラコへようこそ!
〜店先で、ちょこっとおしゃべり〜
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

療育は、子どもにとっても親にとってもメリットがあります。
以下は、療育のベテランで言語聴覚士の中川信子さん(子どもの発達支援を考えるSTの会代表)に聞いたお話です。
●子どもにとってのメリット●
発達凸凹の子は、他の子と同じようにできないことがあり、「できない」という気持ちから自信をなくしがち。「療育」では、その子がちょっと頑張ればできる遊びや課題を提供してもらえます。すると「できた!」「自分もやればできる」という喜びが得られます。それは自己有能感や自己評価の高さにつながり、この後、思春期を迎えるまでの生きる基礎となります。

園や学校では「できない」ことが多く、自尊心を削がれがちな子どもたち。その子たちが、やりたいことを見つけ、自分らしく生きることをささえていくための基礎をつくるのが「療育」です。
看板だけ「療育」をかかげていても、「お預かり」だけだと療育とはよべないということですよね。
子どもの特性にあわせた関わり方をしてくれるのも療育の特徴です。
一般的な子育てでよしとされている「繰り返し頑張る」「我慢する」が、あてはまらないので発達凸凹の子どもたち。ひとりひとりの特性にあわせて、苦手をサポートし、得意なところを伸ばすというかかわりかたをしてくれます。
●親にとってのメリット●
子どもの特性を専門家から聞くことができます。育てにくさは、自分の子育てのせいではなく、特性からきているということもわかります。
そして、これも大きなメリットだと思うのですが、共感しあえるママ友と出会えます。「帽子のゴム紐をいやがる」「感情の切り替えができず、泣き出したらとまらない」「偏食が激しくて食べられるものがない」など。他の場だと「わがまま」「過保護」といわれてしまうかもしれないことも、「うちもそうよ」と言い合えます。情報交換もできます。

昨今、「親の会」に入る人が少なくなったそうです。案外、療育の場で少グループができているのかもしれませんね。ただ、古くからの親の会で活発に活動しているところは入ってくる情報の量がちがいますので、親の会もおすすめです。
「療育とは、丁寧に配慮された子育て」
これは、日本の療育の先駆者である高松鶴吉氏の言葉です。中川さんは高松氏のこの考え方は、今こそ再評価されるべきだし、療育の施設だけではなくすべての園がこの考えで子どもに向き合うことが大事と話しました。
(参照:『発達障害 あんしん子育てガイド』tobiraco編集 小学館)
トビラコ店主
********************************
小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に連載していました。
********************************
ウェブサイト以外でも発信しています。
Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)
LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。
********************************
トビラコが編集した本
『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)

『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)
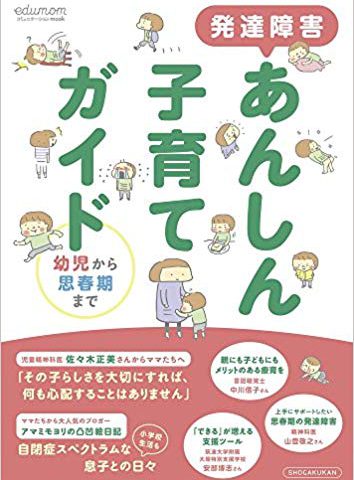
********************************




