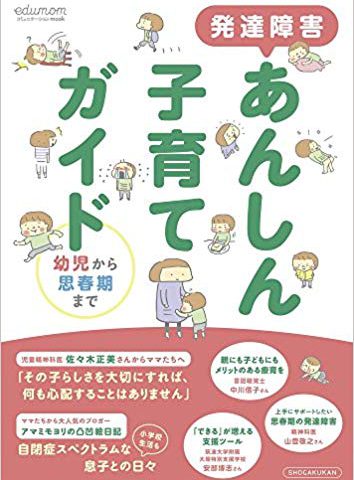「トビラコへようこそ!
〜店先で、ちょこっとおしゃべり〜
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

「合理的配慮」。字面を見ただけで、難しそうと感じる人もいるでしょう。でも、これ、障害のある子(人)、すべてに関係しています。だれでもが、可能な限り受けることができるのです。もちろん、学校教育でも、すでに実施されています。
読み書きに困難があって、その困難が学習をするうえで障害にならないように配慮してもらえるわけです。よく知られたところでは、パソコンです。先生に読み上げてもらうのもありです。
計算ができない計算障害なら、電卓を使うのもありです。別室での試験で時間延長というのもありです。聴覚過敏ならイヤーマフを使うのももちろんありです。

と、わかりやすい例をあげましたが、その子の特性にあわせて、可能な限り応じるようにと文部科学省からのお達しが47都道府県の教育委員会や学校に行き渡っているはずです。
可能な限りというのは、いくら申請してもできないこともあるので「可能な限り」ということになります。
たとえば、車椅子を使っているうちの子のために、エレベーターを設置してほしいと申し出ても、校舎改築などかなりの予算が必要になるので、現実問題、難しいです。では、まったく通らないのかといえば、そんなことはありません。
エレベーターを使わなくてもすむように、教室を1階にしたり、必要に応じて支援員さんに手伝ってもらうなどであれば十分に検討してくれるはずです。
学校で実施される合理的配慮は、だれでもが教育の機会を均等に得るためのものです。
学校だけではなく、役所や鉄道など公的機関はすべて配慮の義務があります。なので、読み書きに困難を抱えている人に、代読や代筆を頼まれたら役所や鉄道の窓口の人は応じる義務があります。
トビラコのサイト「先を照らす人の話」にアップした、高梨智樹さんの「できないこと」をがんばるより「できること」を伸ばせばいい<後編>は、識字障害の智樹さんが合理的配慮を受けて高校受験する話です。

受験にも、もちろん合理的配慮は適用されます。というか、受験にこそ適用されないと、障害のある子が教育を受ける機会を逸してしまいます。なので、受験が遠い先であっても、「合理的配慮」が受けられることを頭のどこかに入れておいてほしいと思います。
とはいうものの、保護者一人の力ではなかなか難しいのが現状(この先、どうなるかはわかりませんが)。やはり信頼のおける先生に味方になっていただくのが得策です。
母親の朱実さんが語っているように、合理程配慮を受けて受験するには、やはり担任、校長先生に相談して、進学先に交渉してもらうのがスムーズ。
もちろん、担任でなくてもいいとは思います。でも、早いうちに相談できる信頼のおける先生を見つけておくことをおすすめします。
トビラコ店主
********************************
小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に連載していました。
********************************
ウェブサイト以外でも発信しています。
Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)
LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。
********************************
トビラコが編集した本
『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)
『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)