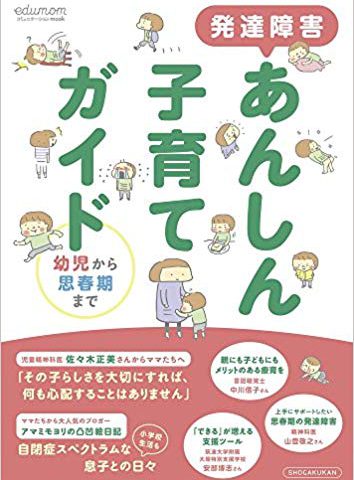「トビラコへようこそ!
〜店先で、ちょこっとおしゃべり〜
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–


(昨日配信したメルマガの記事を再掲載しています)
さまざまな支援があるなかで、表立って語られることのないのが「障害のある子の性の支援」ではないでしょうか。
障害のある子(人)にとって、必要とされているにもかかわらず、です。
学校で教える性の話は、「生命の大切さ」「男女の体の違い」「赤ちゃんができるしくみ」のような、抽象的な話に終始しがちです。
でも、特別支援学校で知的障害のある子を教えている先生は違います。もっと具体的です。
たとえば、ある特別支援学校では、着替えは小学1年性から男女別です。同じ教室で体操着に着替えなくてはならない時には、必ず天井からぶら下がっているカーテンを閉めるように指導しています。
先生に聞いてみると「異性の体に興味を持つ前に、着替えているところは見せない、見ないを徹底させて、あたりまえのマナーとして覚えておくことが大事なんです」とのこと。

翻って家庭ではどうでしょうか。
着替えはおろか、息子がひとりで入浴しているところを、母親がお風呂場に顔をのぞかせて「石鹸まだある?」なんて聞いたりしていないでしょうか? 逆に母親が入浴しているのに息子がドアを開けても注意していないなんてことはないでしょうか? 異性の入浴を見てもいいことを「誤学習」してしまうかもしれません。
家庭内で許されていたことが、外では許されないということはいくらでもあります。なので、家庭の中でも、やはり入浴中はむやみに扉を開けない習慣をつけておいた方がいいと思います。もちろん、着替えているところを見ないということも、です。
公共のトイレでもこんな話があります。
いつも母親と女性用のトイレに入っていた知的障害のある男子高校生が、母親がいないときに女性用のトイレに入って大騒ぎになってしまいました。男の子にしてみれば、お母さんがそばにいないだけで、いつもと同じトイレに入ったのに、なぜ大騒ぎになるのかがわからなかったと思います。公共のトイレも、早いうちから「男子は男性用のトイレで用を足す」を徹底させておいたほうがいいわけです。

トイレの話が出たついでに、先ほどの特別支援学校の男子イレには「かっこよくおしっこしようぜ」という絵カードが貼られています。
その絵カードは、男の子がズボンを下げずに前のチャックだけ開けて用を足している絵が描かれています。先生の話では、あるとき合宿先で高等部の男子全員が、ズボンをおろして用を足している姿を見て「これは、まずい!」と思ったそうです。これも、小さい時に許されていたことが、ある年齢から許されなくなった例です。
家の中と公共を分けて考える。さらに細かくいうと(自分の目しかない)プライベートと(自分以外の目がある)パプリックを分けて行動するように教えることも必要です。
性の支援の第一人者である、山本良典さん(東京都心身障害者福祉センター)は、長年にわたり障害児(者)の支援をしてきたかたです。
山本さんは、障害のある人の性についてタブー視することなく、むしろ積極的に教えるべきと考え、啓蒙活動をしています。山本さんの話も、とても具体的です。
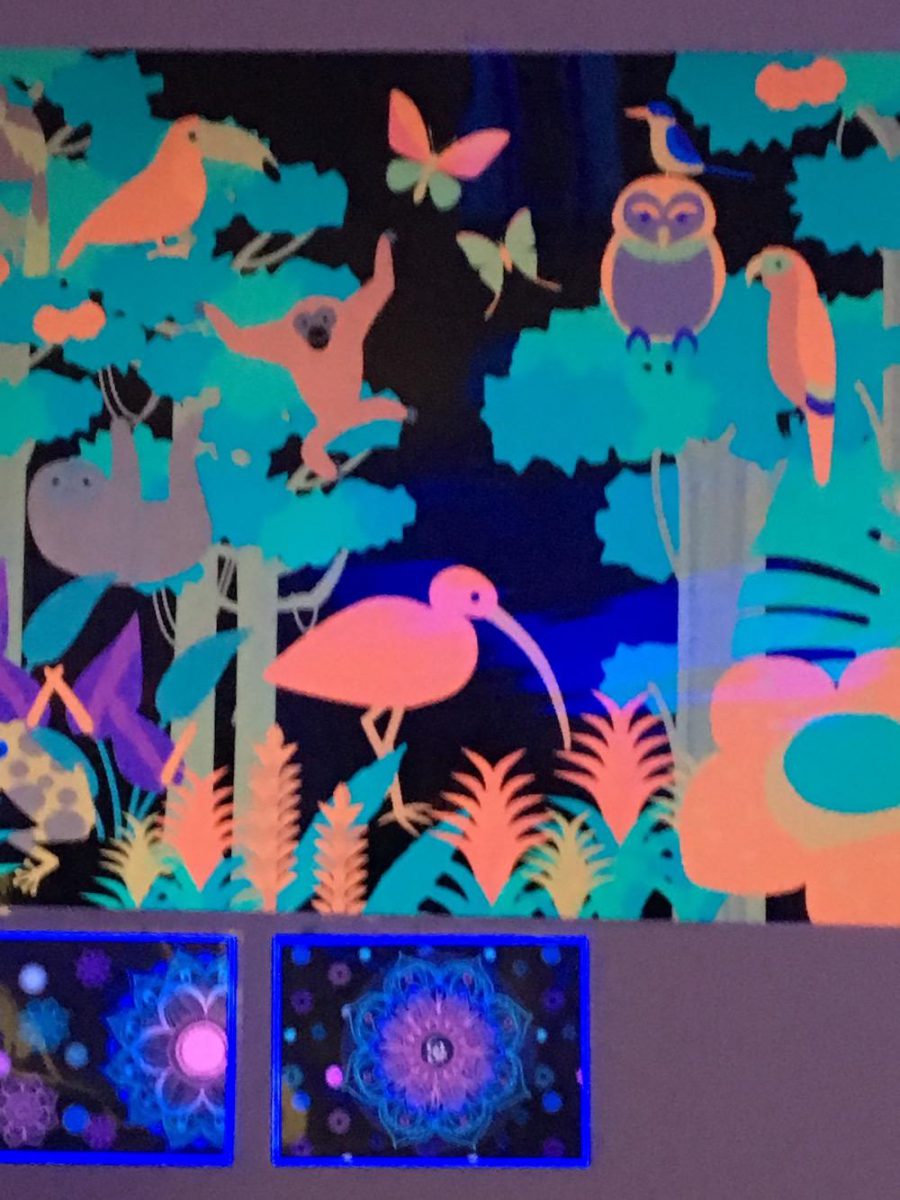
たとえば、プライベートとパブリックについて。ここですら書きにくいことなんですが、自分の性器をいじることやマスターベーションについて。プライベートなら問題なし、でもパプリックなところでやるとまずい。これはきちんと教えなさい、と言っています。なんでもかんでも禁止してしまうことこそ、まずい対応と山本さんは指摘します。
話が横道にそれますが、性器いじりをしたがる子(人)について、山本さんは性の問題だけではなく、別のところに問題がある場合があると述べています。ひとつは、それをすると注意される、つまり注目してもらえるから。もうひとつは、それが「こだわり行動」になってしまっているから。このような場合は、性の問題というよりも、前者ならその子に関心を持つことが少なかったといえるし、後者なら別のことに関心が向くようにするといいのではないかとのこと。


女子は、10代になると「生理」の問題があります。
これも山本さんの話です。
出血=ケガしか知らない自閉症の女の子が、生理がきたら大パニックになります。これを想定した母親は、自分の生理の手当てをトイレで娘に見せながら教えました。
娘が生理になったときに、母親は「お母さんと同じだね」と言ったそうです。お母さんと同じように大人になれたことを受け止めてもらえて、娘さんはうれしかったそうです。そしてナプキンを入れる可愛いポシェットを作ってあげたところ、うれしそうにトイレに行くようになったと、山本さんに報告してくれました。
ここで、余談です。生理用のナプキンは男性の目に触れないようにすることも教えておく必要があると思います。会社勤めをした知的障害のある自閉症の女性が、ティッシュをおく感覚で、生理の日にナプキンを机に上に堂々とおいていた話を聞いたことがあります。それを知った母親があわててポチェットを持たせたとか。
生理用のナプキンは「女の子の秘密」。男子には見せないというのが暗黙の了解であることも、教えておいてほしいと思いますね。


再び、山本さんの話にもどります。
生理についての十分に教えてもらえなかった女の子の話です。
その女性は軽度の知的障害があり、特別支援教育をうけたことがなく、普通教育を受けてきました。職業訓練も受けて仕事もできます。あるとき、彼女が座っていた椅子が汚れていて生理であることにまわりが気づいたそうです。ナプキンを持ってこなかった理由をたずねると、彼女は「お母さんが持たせてくれなかった、だからお母さんが悪い。私は悪くないのに、怒られた」と言ったそうです。
彼女の生理用ナプキンはお母さんがいつも準備し、自分で準備したことはなかったそうです。これでは、生活面で就職はまだ難しいと判断されてしまいました。母親は「娘は仕事ができるのに」と大いに不満だったそうですが、特別支援学校の高等部で3年間生活指導を受けて就職しました。いまは立派に仕事をしているそうです。軽度の知的障害であれば、教えればできるのに、それをしていなかったためにおきたことです。

障害のある子(人)の性の問題は、それだけが独立しているわけではありません。生活自立のことであったり、対人関係のことであったり、周辺のこととつながっています。
タブーにすることは、その子(人)の自立を阻むことになってしまいます。
異性との距離、一定の年齢になったら当然、避妊も含めて教えておくことは必要ではないでしょうか。
教えることは教え、わが子に、好きな人ができたとき、結婚したいといったときに、心から祝福してあげられる親でいたいですよね。
——————————-
最後までお読みいただきありがとうございます。
今週、ご紹介した山本良典さんは「障害者(児)と性」について、おそらく右に出る人はいないというくらいに素晴らしい考察をお持ちのかたです。残念ながら、書籍はかなり古いものしかないのですが、講演活動はされています。機会がありましたら、ぜひお聞きになってください。ここでは、読者の方の年齢層を意識して子どもよりになりましたが、もう少し上の年齢の話をされます。障害のある人の性の話をタブーにするのではなく、豊かな対人関係を築く延長に「性のこと」があるというスタンスです。
——————————-
トビラコ店主
********************************
小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に連載していました。
********************************
ウェブサイト以外でも発信しています。
会員登録された方にはメルマガ(無料)配信しております。会員登録はこちらから。
*会員登録はこちらから。お買い物いただかなくても登録できます。
Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)
LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。
********************************
トビラコが編集した本
『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)
『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)