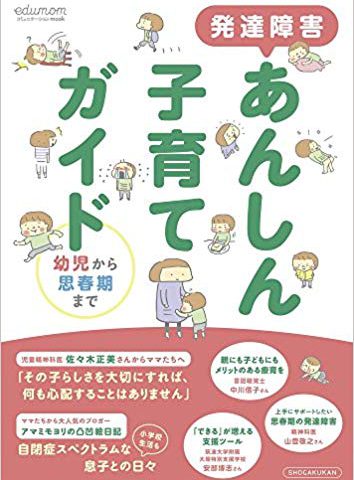~店先で、ちょこっとおしゃべり~
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

「待つ」ということについて、子育て雑誌を編集していた時代に、よく特集を組みました。
そのほとんどが「待つ子育て」というものでした。子どもが自発的にできるようになるまで「待つ」ということであったり、「早く、早く」といわれなくても、できるようになる環境づくりであったり。
親が子どもの育ちを、見守って、待つということに集約されると思います。
さんざん特集しながら抜け落ちていたことがあることに、ある本を読んで気づきました。
「待つことができる子」という視点です。
そのことを教えてくれた本が『芹沢俊介 養育を語る 理論篇Ⅰ』(株式会社オプコード研究所)です。芹沢俊介さんは、犯罪(家族が絡んだものが多い)、教育、家族問題をとりあげている評論家であり思想家です。私も、何度かお目にかかったり、勉強会に参加したりしたことがあります。穏やかな佇まい、優しい語り口とは裏腹に、鋭い論考でバサバサと斬っていくことで知られた人です。
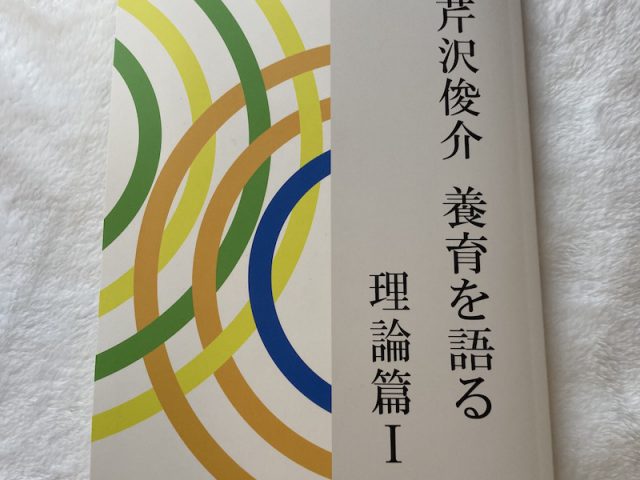
その芹沢さんが、勉強会や講演会などで話したことをまとめたのが本書です。「子育て」ではなく「養育」という点がポイントです。子育てよりも、もう少し広く深く、「子どもが育つ」ということを語っている本です。理論篇の他に事件篇も何冊かでています。事件篇は、子育てや家族問題が絡んだ事件をとりあげて、そこから「養育」を語っています。こちらも大変に興味深い本です。
前置きが長くなりましたが、理論篇に掲載されている「待つ」ということについて。
「待つ」というのは、信頼関係がなければできないとしたうえで、子どもに「待たせる訓練」をさせることについて、次のように鋭く批判しています。
訓練とか教育では、待てる子どもは作れない。待たせる訓練のたまものとしての待つは、大人や教師の指令や命令によって作られた習慣的なもの、自発的なものではないのです。
信頼によって形成された「待つ」は、誰を待つか、なぜ待つかが子どもにとって明瞭です。信頼だけが本当の意味での待つ時間を長くしていくことが出来るのです。そのためには、繰り返せば、母親が、ないしは受け止め手が、その役割をしっかりと果たすこと。子どもを待たせないこと、子どもが必要な時にそこに一緒にいること、そのことしかないのです。(『芹沢俊介 養育を語る 理論篇Ⅰ』より)
ひとつ注釈を加えると、ここでいう「子どもを待たせないこと」は、相手がいつあらわれるかわからないような不安な時間をつくらないということでもあります。芹沢さんは、養育(子育て含む)でなにより大切なのは、信頼関係であり、子どもに安心を提供することだと本書で繰り返し語っています。
さらに、付け加えると、信頼関係はそのままの自分を受け止めてもらえる関係にこそ築かれるのであって、養育者(親も含む)の思う「いい子」にしていたときだけ受け止めてもらえるというのでは、信頼関係は築けないと芹沢さんは語っています。
こういう話は、親自身の育てられ方にも関わってくるかもしれませんね。親の思い描くいい子であるときだけ受け止めてもらえて、そうでないときには(うっすらとにせよ)受け止めてもらえなかった(あるいは拒絶された、あるいはいい顔されなかった)。とても根深い問題だと思います。
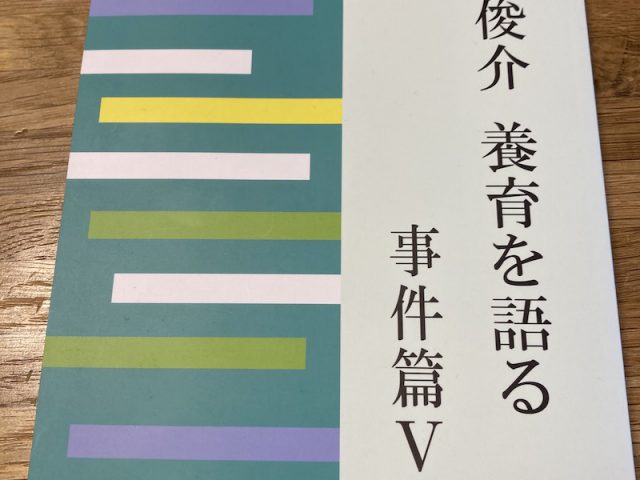
芹澤俊介 養育を語るシリーズ。これは事件からみた養育です。相模原事件についても語っています。これほど深い考察をした人はいないと思います。
トビラコ店主
********************************
小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に連載していました。
********************************
ウェブサイト以外でも発信しています。
会員登録された方にはメルマガ(無料)配信しております。
*会員登録はこちらから。お買い物いただかなくても登録できます。
Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)
LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。
********************************
トビラコが編集した本
『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)
『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)