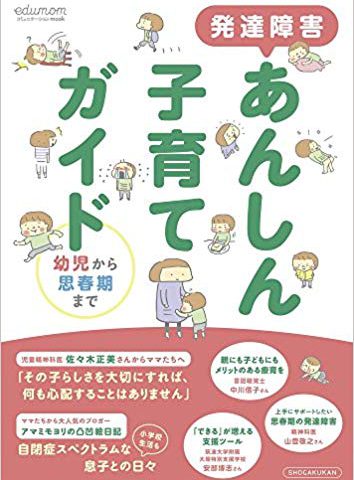トビラコへ、ようこそ
~店先で、ちょこっとおしゃべり~
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

おすすめのオンラインセミナーのご紹介です。
ちょっと専門家向けになるかもしれませんが、保護者でも十分に参加する意義のあるセミナーです。
子どもの育ちについて〜発達マイノリティの子どもとその保護者への生涯にわたる支援〜
講師の中川信子さんは、ベテランの言語聴覚士で「子どもの発達支援を考えるSTの会」の代表です。
*STとは、Speech Therapistの略で言語聴覚士。
中川信子さんは、ベテランの言語聴覚士でありながら、ほとんど専門用語を使いません。専門用語や難しい言い回しをしなくても、伝えるべきことをきちんと伝えられる人とも言えます。
だから、専門家だけでなく専門外の人たちにも人気があるんですよね。
セミナーの案内に掲載されているメッセージに、中川さんの思いが集約されていて、このメッセージに感動してしまいました。
【中川信子先生からのメッセージ】
「療育とは丁寧に配慮された子育てである」(故・高松鶴吉先生のことば)は皆さんご存じですね。「丁寧に配慮された」の部分は「特別支援」と言いかえることができるでしょう。
でも、もうそろそろ「特別支援教育」の「特別」を取って、すべての子ども対象の支援教育にしていこうではないかという声も強まっています。私も同感。
今回は、すべての子ども(多数派。マジョリティ)の側から、「子どもの育ち」を俯瞰的に見ながら、併せて、気がかりのある子ども、障害がある(かもしれない)子どもたち(少数派。発達マイノリティ)のことも見ていこうと思います。
「この子ら【に】世の光を ではない。この子ら【を】世の光に。」
福祉が不備だった時代を切り開いた故・糸賀一雄さんのことばを、今、再び思い出したいものです。子育て、療育、教育のすべてを発達マイノリティ、障害がある(かもしれない)子を中心に組み立てなおすべき時期に来ている、という意味で。
「子どものいる所には、必ず、障害のある子どもがいるはずだ」。旧知の友人であるあるSTが言ったことばです。私は仲間たちと一緒に地元狛江で地域活動をして来ましたが、このことを常に念頭においてやってきました。どうして「地域」にコミットしなければならないと思うのか。そのことについてもお話しできたらと思います。
子どもの育ちについて 〜発達マイノリティの子どもとその保護者への生涯にわたる支援〜」発達療育実践研究会 6月度 より引用
「療育」の根本ってなに? といったときに「丁寧に配慮」されていることなんですよね。〇〇式とか、なんとかメソッドとかに子どもをあわせるのではなく、子どもにあわせた配慮こそが、療育。だとすれば、たしかに、ひとりひとりが「特別」といえるわけで、「特別」ということを、ことさらいわなくてもいいのかもしれません。ことさらいわなくても配慮されているのが、豊かな社会といえるのかもしれませんね。
お時間が許せば、ぜひ中川さんのセミナーにご参加を。
トビラコ店主
********************************
『PriPriパレット』(世界文化社)にトビラコ店主の「ちょっとためしてみませんか!」連載中
小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に
【発達障害の子の小学校入学】学習につまづかない「ノート・日記・下じき」選びで工夫しよう!をアップ!
********************************
ウェブサイト以外でも発信しています。
会員登録された方にはメルマガ(無料)配信しております。
*会員登録はこちらから。お買い物いただかなくても登録できます。
Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)
LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。
********************************
トビラコが編集した本
『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)
『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)