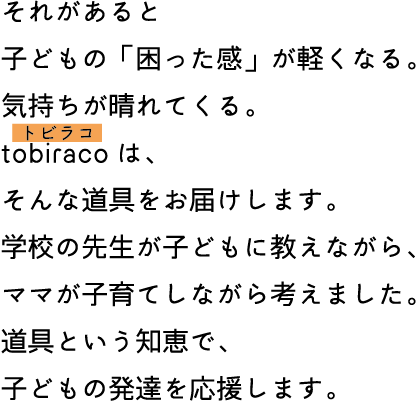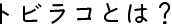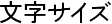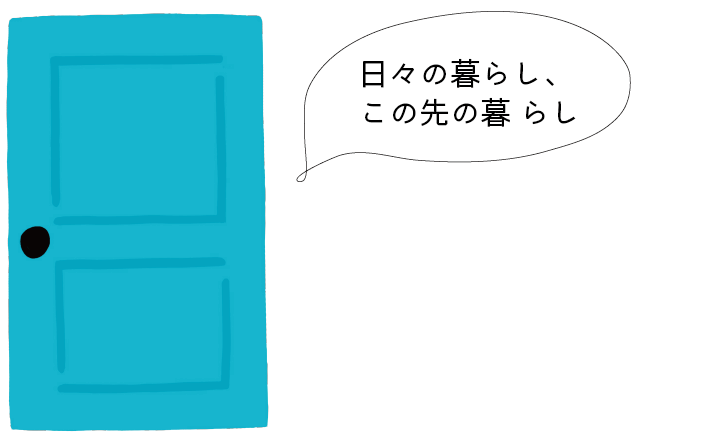tobiracoのおすすめ棚
子どもにとことん寄り添う「放課後等デイ」。
映画「ゆうやけ子どもクラブ!」が教えてくれたこと
障害のある子の放課後活動を支援する、放課後等デイサービス(放デイ)が雨後の筍のごとく増えています。同時に問題となっているのが質の低下。「起業3年、年商3億」「低リスク、ハイリターン」とのうたい文句で、補助金目当てに参入してくる事業所が後をたちません。
障害のある子の成長はゆっくりです。ぎりぎりの人件費で効率よくお金儲けをしようとすると「ゆっくり」に寄り添う人も時間も確保できなくなり、その結果、支援の質が下がってしまいます。

40年前に設立された、障害のある子の放課後の居場所「ゆうやけ子どもクラブ」
「障害のある子の放課後の居場所がほしい」。親たちの切実な願いから生まれた「ゆうやけ子どもクラブ」(東京都小平市)は「放課後デイサービス」の先駆けです。「放課後等デイサービス」という制度も名前も生まれるずっと前、1978年に子ども4人とボランティア数人で「遊びの会」という名で誕生しました。この度「ゆうやけ子どもクラブ」の1年間を追ったドキュメンタリー映画『ゆうやけ子どもクラブ!』(監督・井手洋子)が完成。
質の高い支援は、子どもの「ゆっくり」に寄り添えることであり、子どもへの深い理解なしには成り立たないことを、この映画「ゆうやけ子どもクラブ!」は教えてくれます。
お金儲けとは無縁であるがゆえに、存続に暗雲が立ち込める苦しい場面も出てくるのですが。
ダメ出しがない、指示がない
安心して泣き叫ぶことができる場
「ゆうやけ子どもクラブ」は、2019年現在、3カ所の事業所に発達障害、知的障害の6歳〜18歳の子、68人が通い、職員の数は40人(常勤8人、非常勤32人)にまで増えています。映画は、「ゆうやけ子どもクラブ」誕生以来変わらない理念である「子どもとどこまでも一緒」の活動を、1年半近くかけて追っています。

泣き出した子に「いないいないばあ」であやす女の子たち。
年齢も障害の特性も違う子どもたちを受け入れながら、徹底して子どもたちの自発性を大切にする「ゆうやけ子どもクラブ」。
職員と一緒にダンゴムシを探しに行く子ども。買い物ごっこを楽しむ子。輪になってフォークダンスに興じる子どもたち。別々のことをやっていながらも、大家族のようなあたたかさがあります。
映画では、職員の口からは、ダメ出しも、指示の場面もありません。「子どもを受容する」とはこういうことなんだと思わせてくれます。
障害の特性が否定されることのない場では、子どもは安心して泣き叫ぶこともできます。泣き叫んでいる子を慰める子、泣きたいだけ泣けばいいさとばかりに、そばにいて見ているだけの子もいます。
擬似大家族の場は、自然にできているわけではありません。「場の力」を支えているのは、職員たちの子ども理解にかける高い熱量であることが、ミーティングのシーンでわかります。
ひとりひとりの子どもの様子を記録したノートは数年分にも及びます。気になる子がいると数年前まで遡って分析し、職員たちで共有するようにしているのです。手間ひまかけた「見えない支援」が根っこのように張り巡らされてこその「場の力」なわけです。

冬休み、みんなの前で会の始まりを告げる子。右は村岡真治代表。
言葉をほとんど発しなくとも、受け止めることがコミュニケーション
映画は、3人の自閉症の小学生にフォーカスしています。
言葉をほとんど発することがないガクくんは、散歩が日課。言葉はなくても「あっちに行きたい」「こっちに行きたい」「川をのぞいてみたい」「公園の水浴び場で水にさわりたい」。望みはたくさんあって、職員の手を引いて行きたい方向を指差します。散歩の様子を長回しで撮り続けるカメラから、ガクくんのわずかな表情の変化も伝わってきます。
「散歩の日は、安心するのか、10分で寝ます」と話すお父さん。以前は、寝つきが悪かったそうです。

職員に背負われて、川をのぞきこむガクくん。
一方、聴覚過敏の特性もあるカンちゃんは、こだわりが強く、給湯室で水を出しながら、狭い空間を行ったり来たり。何度も時計を確認しないと気がすみません。
見通しが立たないと彼が不安になることを知っている職員は、これからすることを言葉にしてカンちゃんを安心させます。
「1番、着替え、2番、おやつ、・・・6番お母さんが迎えにくる」というように。

音が混ざりあうのが苦手なカンちゃん。
そして、ヒカリくんは、大の電車好き。積み木でひたすら駅舎や線路を作り続けています。積み木で床を叩くのも電車のリズムで、泣くのも電車の走行音(母親談)。子どもたちが輪になってフォークダンスをしている横で、ひたすら積み木の電車に没頭しています。
職員の手帳には駅名と路線がびっしりと書きこまれ、ヒカリくんの好きなものにとことんつきあっていることがわかります。

積み木に熱中しながらもまわりの子も気になるヒカリくん。
3人とも言葉はないけれども、自分の思いを受け止めてもらっています。気持ちのやりとりをしています。これもまた、コミュニケーションのひとつであり、寄り添う人との関わりで子どもが成長していくことがひしひしと伝わってきます。
「モノにしか興味をもたなかった」ヒカリくんが、手を引いてくれるようになったとうれしそうに話すお父さんも登場。映画で語られる保護者たちの細かなエピソードのひとつひとつが、障害をもつ子の親に響くと思います。
障害を知らない監督が、
先入観なしで、子どもをまるごと記録
監督の井手洋子さんは、障害をとりあげた長編映画を撮るのは初めてです。それどころか「放課後等デイサービス」の存在すら知らなかったといいます。
代表作「ショージとタカオ」(2010年)は、殺人犯にされた2人が無罪を訴え続け仮釈放された14年間(1996ー2010)を追った記録映画です。
たまたま「ゆうやけ子どもクラブ」40周年記念行事の映像を頼まれたのがきっかけで、この映画を撮ることになりました。でも、何をどう撮っていいのかがわからなかったといいます。
ヒントになったのは、「ゆうやけ子どもクラブ」の村岡真治代表の次の言葉です。
「放課後活動は、限られた範囲内のことだけやればいいというのではなく、子どもについていき、子どもとどこまでも飛んでいく覚悟が必要」
「子どもにどこまでもついていく」。井手監督はその通りに撮影しました。どこまでも、どこまでも子どもを追い続け、カメラマンの肩が故障するほどフィルムを回しました。「子どもについていって、子どもとどこまでも飛んでいく」は、「ゆうやけ子どもクラブ」の姿そのものです。

耳を抑えながらも、みんなの中に入ろうとする聴覚過敏のカンちゃん。
先入観がなかったことが、むしろよかったのかもしれません。障害の特性だけに焦点を当てることなく、ひとりひとりの子どもを追い続けた結果、子どもたちの成長した姿が映し出されているのす。
給湯室にこもっていたカンちゃん、電車と積み木にしか興味がないように見えたヒカリくん。やがてみんなの輪の中に入っていきます。
「見てないようで(フォークダンスの輪)を見ていたんですね。(輪の中に入りたい)気持ちをつみあげていたんですね」という職員もまたヒカリくんのよき理解者です。

年齢も障害の特性も違う子たちが輪になって楽しむ、恒例のフォークダンス。
子どもにとって、最良の環境とは、とことん寄り添ってくれる人がいること。自分を受け止めてくれる場があること。これこそが質の高い支援であることを、この映画「ゆうやけ子どもクラブ!」は、静かにあたたかく語りかけてくれます。
映画「ゆうやけ子どもクラブ!」
ホームページ、こちらをご覧ください
小学館の子育てサイト「HugKum(はぐくむ)」に紹介した記事を転載しています。
文/平野佳代子